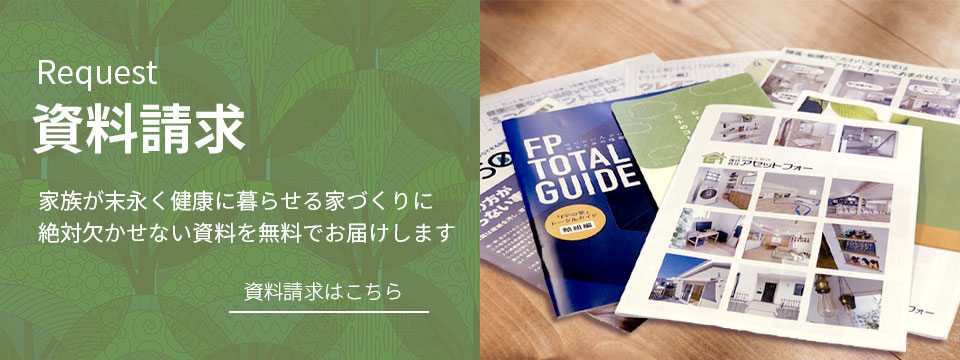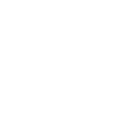ここで開発されたのが米松乾燥材の商品名がドライ・ビームです。
全ての製品に強度(E110以上)・含水率(SD20%)を表示し、シリアルナンバーも印字しています。
工場でいつプレナーを掛け、どの乾燥機で乾燥したかなど製造工程が確認できるので、問題が発生した時に、そのスケジュール内容が分かるようになっているらしい・・・。
凄い管理体制ですよね。
先程の写真にあったSD20は、含水率20%を示している訳です。
ドライビームには中国木材の『無垢へのこだわり』と『乾燥へのこだわり』が込められているそうです。
以下、ドライビームのページから抜粋します。
木は本当にすばらしい性能を持つ建築材料です。
熱を伝えにくい
弾力性がある
塩害に強い
衝撃を吸収する
調湿効果がある
音をやさしくする
紫外線をやわらげる
森林浴効果がある
などといった優れた性能をたくさん持っています。
しかし、伐採したばかりの木は時間の経過によって
縮んだり
反ったり
曲がったり
ねじれたり
割れたりする
性質も持っています。
これは木に含まれている水分が主な原因です。
木は乾いていく過程で繊維方向によって収縮の割合が異なるために「くるい」が発生するのです。
昔の大工さんは木の乾燥と収縮の関係を知っていて、棟上した後すぐには内装工事にとりかからず、半年以上放っておきました。
その間に木を十分乾燥させて構造の安定を図ることが、昔の大工さんの知恵だったのです。
こうして乾燥させた木材は、現代の数値で表現すると含水率15%~20の状態になっていたと考えられます。
しかし、今はスピードの時代。
構造体でゆっくり乾かすというこの伝統的な家造りが難しくなってしまいました。
そこで、前もってしっかり乾燥させた木材が必要となってくるのです。
これが乾燥へのこだわりです。
そして無垢へのこだわりがコレ!
①有害物質をまったく含んでいない
②ぬくもりがある
③調湿作用に優れている
④本物の素材感が楽しめる
⑤豊かな質感で手触りがよい
⑥時と共に心地よく古びていく
⑦解体時にも環境に優しい
弊社の理念に合致しているんです。
この他にも、こだわりが書かれてます。
是非、元ページをご確認ください。
私自身、全ての横架材をドライビームにしたいと思っています。
でも、まだ決断する事が出来ません。
高気密住宅にとって、構造材の狂いは致命的。
狂いは隙間に繋がりますから・・・。
この点を憂慮して、小屋梁から上にのみドライビームを採用し、その他の構造材は集成材を採用しています。
乾燥した小片を貼り合わせた構造用集成材の方が、より狂いにくいのは確かなんですよね。
でも、ドライビームの方が優れている点も多々あります。
もう一度、検討してみようかな?